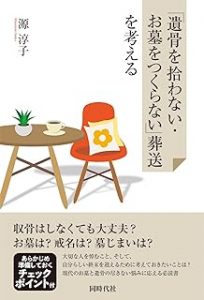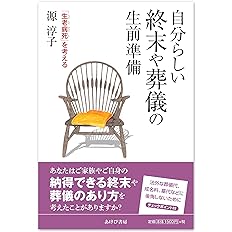5月、今月の1枚ー「今年もアマリリスが咲きました」
「今年もアマリリスが咲きました」
5月は快適な季節です。地球はどんどん熱さを増しているようですが、5月はつかの間の本当に過ごしやすいいい季節です。しかし、桜は早々に3月末で若葉になってしまいましたし、4月に5月(さつき)がピークでした。どんどん季節が早送りになっていますが、花の早送りぐらいならいいのですが、今年の夏は有史以来の猛烈な暑さになるそうで、今からそれが恐怖です。
しかしとにかく今は5月、青空にそよ風のいい季節です。3年前の5月、夫が亡くなりました。あの日も玄関先のアマリリスが見事に咲いていました。今日も同じようにアマリリスが咲いています。アマリリスは、ギリシャ神話に出てくる羊飼いの少女の名前だそうですが、花言は、「おしゃべり」「すばらしく美しい」などだそうです。太い茎に堂々とした大輪の鮮やかな赤い花を左右対称に咲かせます。心が晴れ晴れとする見事な咲きっぷりです。
金谷千慧子『アマリリスが今年も咲きました』 F20号
夫が亡くなって、もう(?)、やっと(?)3年経ちました
今月の1枚は、夫の逝去からの3年間を思いながら、アマリリスの花を描きました。私が慌てふためいたあの日の朝も、玄関のドアを開けるやまっすぐに立派に咲いているアマリリスが目に飛び込んできました。その後1か月も咲き誇っていたアマリリスです。玄関あたりはその後リフォームで変えてしまいましたが、描いた情景は3年前のままにしました。紫陽花が繁茂していて、外出するのが苦痛になっていた私をさらに家に閉じ込めるように玄関口をふさいでいました。大木になった松の木はあたりを薄暗くしていました。2年前のリフォームで、紫陽花もほとんど伐採し、大木も引き抜き、門扉も変えました。その後、玄関の前方の家並みも変わりました。新しく5階だてが並びました。
夫が亡くなって3年が経ちました。そういえば2年を経たら、3回忌という法要をするのが普通のようですが、私は、なんにもせずに、3年を過ごしてきました。亡くなった直後の法要も何もしませんでした。何もしないまま、これからもずっとこのまま過ごしたいと思っています。夫は亡くなりましたが、戒名を得て、仏になって成仏したのでもなく、いつまでも生前の姿のままで、私の中で生きています。それで十分です。その方がいいです。無理やり仏壇の中に閉じ込めて、意味の分からない読経を何度も流すことなど、全く不要だと思っています。
もちろん、私の死亡時も同じことを希望しています。お葬式は不要です。骨も拾わないでください。お墓もいりません。死後の法要もいりません。これはすでに公正証書遺言に付帯事項として記載してあります。それが私の希望です。
亡くなった夫とは、いろいろ話し合って合意していました。「末期の延命治療は必要ない」「仏式の葬式はしてほしくない」「戒名は要らない」「お墓は要らない」とかです。ところが、死期が近づいたある日、「やっぱり骨は四天王寺さんに入れてほしい」と言ったのです。それで(無宗教のリモート)葬儀の後、遺骨を拾うことになってしまったのですが、私は遺骨を拾わないでほしいと願っています。コロナ禍のさなかで家族以外参加できない状態でしたが、お花だけたっぷりにしました。あれから、やっと(?)、もう(?)3年が過ぎました。そして私が今度は夫が亡くなった年齢に到達しました。
書籍紹介 源淳子著『遺骨を拾わない・お墓をつくらない」葬送を考える』
同時代社 2024年4月30日刊 本体1400円+税)
このブログの原稿を書いているとき、長年の友人源 淳子さんが近著を送ってくれました。彼女も女性学の教師として大学や女性センター(男女共同参画センター)でご一緒していました。なかでも関西大学ではご一緒の時期が長かったのです。彼女は浄土真宗のお寺の子どもとして生まれで、得度(注)を受けた僧侶でもあるのです。
(注)得度とは、仏教で僧侶となるための儀式・手続きのことで、この儀式を経て一般の在家(ざいけ)から僧侶になります。得度で、仏教の教えを深く学び、他者に広める役割(布教)を担います。
しかしフェミニズムに出会い、仏教の中にある女性差別に気づき始めてからは、ジェンダーの視点で生きることを決意し、信心は持たないと決めたのだそうです。その後知り合った仏教関係の新聞社に勤めていた「つれあい」さんと生活するようになり、彼もフェミニストになっていったそうです。その彼に先立たれるという不幸に直面し、勉強した親鸞の教えと巷のお寺さんの説教・説話との違いを克服する実践行動に出ることになります。「つれあいの遺骨を拾わない」というのも、二人で話し合った結果を実施したということなのです。「骨を拾わない・お墓をつくらない」「無宗教の葬儀」こそが、真の宗教的自立とフェミニズムの結論だといいっています。フェミニズムでいう自立は、経済的自立、生活的自立、精神的自立、性的自立を指しますが、宗教的自立とは、まず宗教を知ること、宗教を学ぶこと、そのうえで信仰を持つ、持たないをきちんと選択することだといいます。宗教を見極める力を持つということです。この第6章は彼女の人生を賭ける圧巻の筆力だと思います。私もこの本を読んで本当にそう思えるようになりました。これから高齢を生きる方にはぜひ読んで頂きたい書籍です。彼女は「つれあい」をなくした直後に「自分らしい終末や葬儀の生前準備」という書籍を著しています。この書籍も実際に役立つことばかりです。お勧めです。
関連記事
-

-
断捨離って、必要なものを残して大切に扱うこと
断捨離! この今年の夏の暑いさなか、娘とともに断捨離に励みました。 まずは、収納 …
-
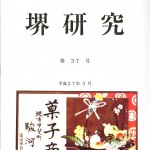
-
与謝野晶子「山の動く日来る」の再来を! その3
論文紹介:平子恭子「與謝野晶子の生育―堺時代の家庭環境および社会(地域)環境―」 …
-

-
母の日
昔、母性神話に悩まされていた。「保育所に預けるなんて、母性というものがない人だ」 …
-

-
2012 – Happy New Year!
Japanese(日本語) Happy New Year! In 2012, p …
-

-
みなさまもお気をつけあそばせ!
2週間アメリカへ行っておりました。西海岸のサンフランシスコに1週間、それからニュ …
-

-
与謝野晶子「山の動く日来る」の再来を! その1
最近、長年与謝野晶子研究をしている方とお付き合いが復活しました。それをきっかけに …
-

-
フェミニズムとわたしと油絵(2013~2023)(その5)
NHK日曜美術館「ウォーホルの遺言 〜分断と格差へのまなざし〜」(2023.1. …
-

-
Golden Midosuji
Japanese(日本語) It’s Dec. 9, 2011 today Wi …
-

-
ちょっと騒ぎすぎじゃないの?令和 (女性と仕事研究所同窓会、もうすぐ)
このところ毎日、毎日皇室の報道と「平成の歴史」「さよなら平成」だの「新しい令和の …
-
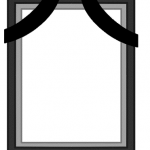
-
夫の死にあたふた(1~3)
夫死亡、コロナ禍の手作り葬儀、新しい葬儀の時代がくるか 弁護士の夫 …