新しい“うねり”を奏でてほしい(4)
85年を生きた。今なおNPOと女性の活躍を熱望する日々
最近の私の絵画作品を紹介しながら (F20号『そんなに嬉しいの?』)
政治団体「再生の道」を立ち上げた石丸伸二氏は、日本の再生に教育への投資を掲げていますが、私も共感する者の一人です。彼の政策でコミュニティ・カレッジの名称はまだお目にかかれませんが、職業教育の強化を強調しています。今回はコミュニティ・カレッジの原則的な話を進めたいと思います。
1 アメリカにおけるコミュニティ・カレッジ
アメリカ史上最大の成功例だといわれる「コミュニティ・カレッジ」の最初は1901年設立のイリノイ州のJoliet Junior College(ジュリエット短期大学)だといわれています。ここは今も16,000人の学生を抱え地域の大学教育に大きく貢献しています。
筆者が訪れた1989年時点では全米で2000か所だといってました。このときはニューヨーク市の4か所を訪問しましたが、どこも学生数(フルタイム&パートタイム)が1万~2万人と大型で、教室では10人程ずつが、200以上のコースに分かれて職業スキルを習得していました。
Laguardia community college,(ラガーディアCC)N・Y
Christchurch Community College (New Zealand)(クライストチャーチCC)
(交通の便が良い。「この街の女性でこの場所を知らない人などいないよ」と)
London CC-PLUME(England)(カレッジの建物が取り囲むように保育所が。子どもの様子を見守りながら受講できる、という)(photo 3)
その後アメリカでは「教育はすべての人に等しく与えられる権利」といわれる時代を迎え、コミュニティ・カレッジは「すべての人に門戸を開く」大学になりました。また同じ理由から、学費もできる限り安く設定されています。さらに1947年には、「コミュニティ・カレッジは、すべてのアメリカ国民が「通学できる」位置につくられるべきということで、都市部を中心に通学しやすいところに設けられるようになりました。コミュニティ・カレッジは、「誰でも」「いつでも」「どこでも」「安価に」学べる大学なので、入学者の選抜はなく、全入制(open admission)です。コミュニティ・カレッジを卒業すれば、原則、四年制大学の3年生に編入できます。コミュニティ・カレッジは、当初から成人教育や生涯教育に力を注いできました。授業を夕方や週末に開講するなどして、働きながら通いやすいようにさまざまな便宜をはかっています。最近ではオンラインの授業が、忙しい社会人学生の間で人気です。また時代の流れや社会の変化に応じて、ニーズの高い職業スキルの訓練に力を注いだり、カリキュラムを新設したりといった柔軟性も、コミュニティ・カレッジの持ち味です。中堅労働者の職業スキルは、ほぼコミュニティ・カレッジで習得されているといえます。
2 「コミュニティ・カレッジ」の特徴
●通いやすく安価(学費が低廉)
●職業スキルの実践と獲得(ほぼ全産業の中堅労働者を育てる)
●就職・転職支援が強力になされる
●柔軟な時間割(夜間・オンライン)
●様々な年代層がともに学べる(フルタイム・パートタイム学生可)
●特に援助が必要な階層への支援が充実(EX保育所、next step center等)
●地域密着型で、地域コミュニティが経営に深くかかわる。自宅通学が可能
地域に根差した職業教育・雇用が確保されることにより地域経済(中小企業)の持続可能性が確保でき、女性やシニアの社会復帰で、家計所得・消費力の向上が見込まれます。中小企業の技術力・人材確保により、生産性向上・国際競争力の強化つながります。
●あらたな形態の学校
大学(理論中心)や専門学校(実践的ではあるが学び直しには不向き)、短大(女性向け傾向、選択肢が少ない)、公的職業訓練(短期・実技偏重で、進学・継続学習や人生をゆっくり考えなすのは無理)でもない、もう一つの新たなリカレント(やり直し)や自立への学校です。
3 今、日本に「コミュニティ・カレッジ」が必要なわけ
●人口減少・高齢化で、新たに職業能力のレベルを高める必要性
転換期にある日本には、「コミュニティ・カレッジ」が必要になっています。人口減少、高齢化により労働力不足が顕著になっており、生産性の維持ができなくなっています。これは工業生産だけではなく農業も含めて、サービス業でも働き手が不足しています。少なくなった人口に転換期に対応できる高度な即戦力としての職業能力を付与しなければなりません。東京一極集中と地方の経済の衰退は著しくなっており、コミュニティ・カレッジは全国規模で必要なのです。
●雇用と教育のミスマッチ
企業では人手不足ですが、一方で非正規でしか仕事がない、職業スキルを持たず就職できない若者や再就職に苦しむ女性や中高年が多数います。産業構造の変化によりITやグリーン化に対する職業教育が追いついていません。従来の終身雇用形態で成り立っていた企業内職業教育は今では成り立たず、企業外部で育成される即戦力が必要なのです。
●非正規雇用の増加と所得格差の拡大
職業教育の機会に恵まれない層は、経済的に不利な立場に固定されてしまっており、貧困層が増加しています。女性の貧困化が顕著になっています。所得格差が拡大しています。
●経済再生には、すべての人に「リカレント教育」を
生涯にわたり学び直しができる職業教育システムの構築で、人材育成が急務です。東京一極集中から脱却し、地方創生を実現するためには、地域で学び、働き、豊かに暮らせる社会の実現を必須です。ジェンダー・年齢・階層などにかかわらず誰もが社会で活躍できる社会を目指すときです(Inclusion:包摂)
●特に日本における課題
コミュニティ・カレッジは日本再生の最大の政治課題・経済政策であり、日本の経済再生に不可欠なインフラです。若年人口の減少、社会の多様化、雇用の流動化、地方の衰退という複合的な課題に対して、柔軟で実践的な新たな地域に根を張った教育の仕組みが求められるのです。ただ日本ではコミュニティ・カレッジは政策としての成熟していないので、国・自治体による制度整備と予算措置が必要です。また大学や企業、NPOとの連携が必須です。さらに通いやすさを考慮すると、地域分散型の設備が必要です。またキャリア支援や保育施設、相談事業等の周辺支援の整備も要になります。
(参考:木田竜太郎「日本型コミュニティ・カレッジ構想とキャリア支援教育~短期大学『地域総合科学科』をめぐって 早稲田教育評論第27巻第1号)
4 特に、女性に「コミュニティ・カレッジ」が役立つ
●学び直し(リカレント教育)に最適
結婚・出産・育児等で一時的にキャリアを離れた女性が、再就職や転職に向けたスキル習得をする場として有効です。IT,保育・介護・医療・語学・ビジネススキル等実践的なコースで習得できます。
●時間的・経済的な柔軟性
通常の大学より学費が安く、夜間やオンライン授業も多く、子育てやパートタイムの仕事との両立がしやすいのが特徴です。働きながら通える設計になっています。
●多様な年齢・背景の人が通う環境
高校卒業後すぐの学生だけでなく、20~50代以上の女性も多数在席しています。年齢やバックグラウンドに関係なく通いやすく、孤立感が少ないのが特徴です。
●キャリアチェンジの足掛かり
専門資格取得や大学への編入制度が整っています。正社員に戻りたい、別の分野で働きたいと考える女性にとって「通いやすい」のはメリットです。また地域の企業や自治体と連携した就職支援もあり、地元での再就職に有利です。柔軟性のある、学び直しの機会を得て、経済的自立が獲得できます。地域密着で社会参加の再開もできます。保育施設や相談事業も整っています。
コミュニティ・カレッジは、女性が自分らしく働き、自分を生きるための『第2のスタートライン』です。(次回に続きます。コース等の具体化を)
要約:日本の再生にコミュニティ・カレッジが必要だという提言です。特に女性が結婚や育児でキャリアを離れた後も学び直しや再就職を目指せる柔軟な学びの場としてコミュニティ・カレッジの意義や利点を紹介しました。多様な年齢や背景の女性が利用でき、キャリアチェンジや地域での経済再生にも効果的であることを強調しいています。ただ日本ではこれからです。
5 トミーが死んだ
トミーが死んだ
トミーは砂になってしまった
私のトミーが、もういない
なんとしてでも助けたいと一生懸命願った
いやがるお薬もスポイドで少しづつ、少しづつ口に含ませた
ご飯も食べないので、一口づつ流し込んだ
しまいにトコトコ逃げ出して階段を下りて隠れてしまった
病院には抱っこしてタクシーで行った
でも原因不明の蛋白喪失性胃腸症の原因解明はできなかった
決定的な病名が出ないのなら、助かる道はきっとある、と私はやっぱり思っていた
胃腸症9か月目の最後の日、トミーの息が止まった
私の身体もぐちゃぐちゃに溶けてしまった。絶望―――。
トミーが死んだ
私のトミーが死んだ
あんなに可愛かったトミーが死んだ
大切なトミーが死んだ
トミー(10歳と11か月)
6 今月の油絵 『そんなに嬉しいの?』 F20号 2025年6月作成
関連記事
-

-
こんなときだからこそ 国際女性DAY
コロナウイルスが広まる中で コロナウイルスの拡大で世界は一変してしまいました。1 …
-

-
フェミニズムとわたしと油絵(2013~2023)(その10) 世界のジェンダー格差指数、日本、過去最低の125位
「フェミニズと私と油絵」の初校を頑張っています 絵画展でご参加いただいた方に読ん …
-
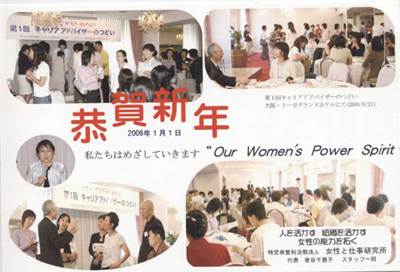
-
寒中お伺い申し上げます
新しい年を迎えました。そして今日は、11年目の阪神大震災の日です。 それぞれの1 …
-
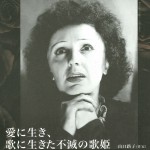
-
ミュージカル「エディット・ピアフ」を堪能しました
私はずっとシャンソンが好きでした。東京にいるとき(単身赴任中)は、四ツ谷にある『 …
-

-
新年おめでとうございます
2023年1月1日 いいお正月をお迎えのことと存じます。今年こそコロナウイルスか …
-

-
夫の死にあたふた(1~3)補足1 理性が導くところなれば、どこへなりとも 参りましょうぞ 菩提樹一葉
夫は語学には長けた人でした。英語との最初の関わりはカソリック系の中学校でシャ …
-

-
新しい“うねり”を奏でてほしい
85年を生きた。今なおNPOと女性の活躍を熱望する日々 最近の私の絵画作品を紹介 …
-

-
寄りかからず。 立て、立ち上がれ!
詩人の茨木のり子さんは2006年2月17日79歳で亡くなった。大阪市の出身。夫死 …
-
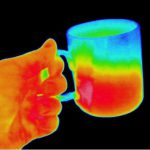
-
暑すぎる! お身体の調子いかがですか
ほんとに暑すぎます。 8月も下旬に入ったのですが、この蒸し暑さは耐え難い苦痛です …
- PREV
- 新しい“うねり”を奏でてほしい(3)
- NEXT
- 新しい“うねり”を奏でてほしい(5)





